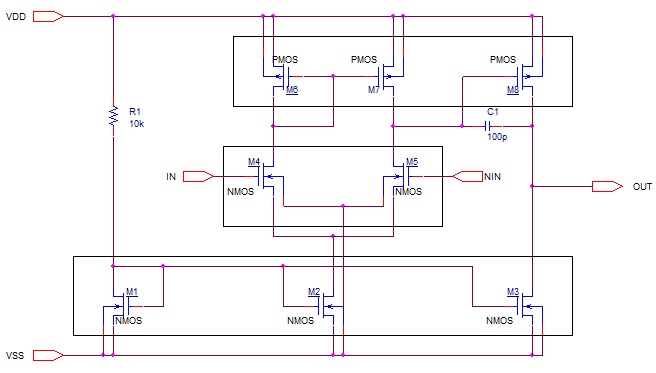アナログ回路の基本はOPアンプですよね。
今や、OPアンプは電池一個で動く定電圧動作のもの、GHzで使える高周波タイプ,電源電圧いっぱいに使えるレールトゥレールタイプ,入出力とも差動動作の全差動タイプ、と用途に合わせて選べば、希望のシステムを構築することができるようになりました。
しかし、OPアンプの内部はどうなっているの? どうしてそう動くの? という疑問を抱かれる方に答えるのに、SPICEシミュレーションはとても役に立ちます。
ただし、実時間で動くものにはならないので、直感的に理解するには無理があります。
そこで、トランジスタレベルでOPアンプを組んでみる方法を紹介してみようと思います。
使うデバイスは、CMOSデジタル4000シリーズの4007です。
これは、デジタルICの中でもロジック素子ではなく、トランジスターアレイが入っています。
NMOSが3個、PMOS が3個、14ピンのDIPパッケージに入っています。
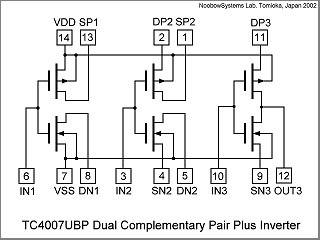
OPアンプには、トランジスターペア(同じチップに入った特性が揃ったトランジスタ対)が必要です。
入力段の差動対、バイアス電流を設定するカレントミラーのところは、特性が揃ったものがないと、うまく作動アンプとして働いてくれません。
ディスクリートのMOSを組み合わせただけでは、オフセットが非常に大きいとか、電流がうまく設定できません。
その点、この4007はひとつのチップの中にペアで使えるトランジスタが入っていて、OPアンプが作れるのです。
4007のPMOSとNMOSのゲートは3セットともゲートが繋がっています。
PMOSのバックゲートはVDDに、NMOSのバックゲートはVSSに繋がっています。
一番左のセットのPMOSのソースはVDDに、NMOSのソースはVSSに繋がっています。
一番右のセットはPMOSとNMOSのドレイン同士が繋がっています。
ひとつの4007のトランジスタペアは、どちらかのMOSしか構成できません。
使わないMOSは電流が流れないように、端子をオープンにするなど配慮が必要です。
ただし、VDDとVSSは電源に接続しなくてはなりません。
4007を使った回路図を示します。(途中)